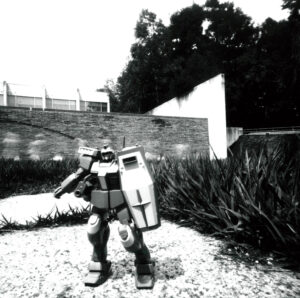Robert Frank ― Why Don’t We Talk About Photography Once Again?
会期:2019年6月29日(土) ~ 9月23日(月・祝)
世界で最も重要な写真家のひとりであり、世代を超えて熱烈に支持されているロバート・フランク。
当館収蔵作品より、未発表の作品を含む106点を展示。
写真家ロバート・フランクは、世界で最も重要な写真家の一人として、多くの同世代および後進の写真家に影響を与え、 そして現在も、世代を問わず熱烈に支持されている写真家です。
1947年、フランクは、23歳でスイスからアメリカ・ニューヨークへ移住し、写真家としてのキャリアをスタートさせます。その後、約15年間集中的に写真を撮影しました。生地スイスからニューヨークへ渡り、南米やヨーロッパへの撮影旅行を重ねた後、自分の写真集を世に出す決意とともに再びアメリカへ戻ります。そして、1958年に写真集『アメリカ人』を発表。自身は、発表直後に映画製作へと身を転じますが、『アメリカ人』は、かつてない大きな衝撃をもたらし、20世紀の写真を大きく変貌させるきっかけとなりました。
『アメリカ人』は、スイスから移住したばかりの若者がアメリカに強く感じた疎外感、不安、そして孤独。写真に表現されたざらざらとした質感と憂鬱な空気は、戦後アメリカ社会の様相を鋭くあぶり出した写真として世界に衝撃を与えました。1950年代のアメリカは、戦後の繁栄と自信にあふれ、一方で黒人差別に反対する公民権運動が勃発。人種問題や戦後の世代・文化が錯綜する、大きな変貌の渦中にありました。アメリカの社会的弱者、恥部的な実態を露にし、しかも写真のシャープさや美しい階調を求めない写真による『アメリカ人』は、米国内で、まさに“炎上”の様相を呈し、酷評されたのです。
しかし、即興詩をつぶやくように直観的なイメージ群と、それらを写真集の中で構成する手法は、全く新たな表現世界を提示していました。ドキュメンタリーでも、メッセージでも、決定的な瞬間でもなく、写真家自身が「何かを感じたら撮る」。あくまでも主観的な写真は、それまでの写真のスタイル、枠組みに捉われない自由さに溢れていました。しかも、大胆さだけでなく、細部までの繊細さや緊張感を併せ持つフランクの写真は、同世代の若者やアーティストを中心に、驚きと共感を得るまでに時間はかかりませんでした。やがて『アメリカ人』は、広く世界に受け入れられ、現在では最も版を重ねた写真集となりました。フランクによる主観的な表現の登場は、現代写真につながる劇的な変化をもたらしたのです。
『アメリカ人』の序文を書き、フランクと同時代の作家ジャック・ケルアックは「ロバート・フランクにおれからのメッセージ:あんた、目があるよ。」(『アメリカンズ』山形浩正訳、宝島社、1993年)とその魅力を表し、また、当館館長であり写真家の細江英公は「見ている人間が見られていると感じる。怖い写真家だ」と、瞬時に本質に迫るフランク作品の特徴を表しています。
フランクは現在94歳ですが、写真・言葉・グラフィックワークを自在に操った写真集が次々と発刊されています。しかし、展覧会の開催は比較的少なく、日本国内での大規模な展覧会は本展が23年ぶりとなります。
本展では、当館の収蔵作品より、これまで写真集に掲載したことのない未発表の作品を含めた106点を展示いたします。作品はすべて撮影当時に近いヴィンテージ・プリントで、当館がまとまった形で展示をするのは、本展が初めてとなります。
これらの作品によって、若き写真家が、模索と挑戦を重ねた初期の歩みと眼差しを辿ります。
本展が、フランク作品の歴史的価値と今日的意義を明確にする貴重な機会となると確信し、また、あらためて写真との深い対話を交わす機会となれば幸いです。

《聖フランシス、ガソリンスタンド、市役所 – ロサンゼルス》1955年
St. Francis, gas station, and City Hall – Los Angeles, 1955
© Robert Frank from The Americans
■展示作品
『アメリカ人』掲載作品・・・・・ 9点
アメリカ・・・・・・・・・・・・ 70点
ペルー・・・・・・・・・・・・・ 3点
パリ・・・・・・・・・・・・・・ 6点
イギリス・・・・・・・・・・・・ 7点
スペイン・・・・・・・・・・・・ 7点
イタリア・・・・・・・・・・・・ 3点
スイス・・・・・・・・・・・・・ 1点
全106点
■ロバート・フランク略歴
1924年、スイス・チューリッヒ生まれ。1947年、23歳の時にアメリカ・ニューヨークに移住。雑誌「ハーパース・バザー」でファッション写真に従事する一方、南米やヨーロッパ各地への撮影旅行を重ねる。1953年にファッション誌の仕事を辞め、フリーランス写真家として「ライフ」「フォーチュン」などの雑誌に寄稿。1955年・56年にグッゲンハイム財団の奨励金を受給し、9ヶ月間アメリカ国内の30州を撮影しながら車で旅し、1958年にフランスで写真集『Les Americains』を、翌年アメリカ版『The Americans』を出版。移民者の目から見たアメリカの姿をありのままに写した一連の写真は反アメリカ的であると酷評されたが、フランクによって示された個人の視点に基づく主観的な写真表現は、リー・フリードランダー、ダイアン・アーバス、ゲイリー・ウィノグランドら後進の写真家に大きな影響を与えた。現在94歳。ニューヨークとカナダのノバ・スコシア州にて、美術家のジューン・リーフとともに暮らしている。
■会期中の無料デー
- 7月7日(日)・・・開館記念日
- 7月28日(日)・・・親子の日
★親子の日とは・・・7月の第4日曜日
年に1度、親と子がともに向かい合う日があったっていい。その日を通じて、すべての親子の絆が強められたらすばらしい。そんな願いを込めて、2003年に、米国人写真家ブルース・オズボーン氏の呼びかけで始まったのが「親子の日」です。 http://www.oyako.org
- 8月11日(日・祝)・・・山の日
会期中のイベント&ワークショップ
■ピンホールカメラ・ワークショップ
身近にある材料で、レンズが無くても写るピンホールカメラを作ってみませんか?暗室でのモノクロ現像も同時に行います。親子での参加もOK! 夏休みの宿題にもどうぞ。
■日時:8月4日(日)10:00~15:00
■講師:当館学芸員
■参加費:1,000円(入館料を含む)/ 友の会・会員は無料
定員10名/ 要予約
■K・MoPAチャリティ・ライブ2019
ピーター・バラカン Live DJ
「ロバート・フランクの写真・アメリカ・それから」
■日時:9月21日(土) 14:00~16:00(途中休憩あり)
■会場:清里フォトアートミュージアム・音楽堂
■出演:ピーター・バラカン(ブロードキャスター)
独自の視点と音楽観で世界の多様な音楽を紹介しているピーター・バラカンさん。バラカンさんが、ロバート・フランクの名前を初めて知ったのは、ローリング・ストーンズが1972年にリリースしたアルバム「メインストリートのならず者 (Exile On Main Street)」のジャケット写真でした。その後、フランクの写真集『アメリカ人』を見て、「アメリカを、アウトサイダーの目で、とても詩的な感性で観察した写真」に、さらに印象を深めたとか。
「レコードというものは、時間の流れの一瞬や、ある時点のスナップ・ショットのようなもの」と言う バラカンさん。写真もレコードも、アーティストが生み出す“ワンシーン”であり、繰り返し楽しむことができ、見る・聴く度に新しいイメージを描き出してくれるものではないでしょうか。
本展展示の作品には、店のウィンドウに飾られたレコードなど、当時の音楽の気配も写し込まれています。実際にどのような音楽が愛されていたのか、また、バラカンさんが、ロバート・フランクの写真からインスピレーションを得た曲をセレクトし、写真、音楽、時代が様々に交差する世界をナヴィゲートしていただきます。
本チャリティの収益は、世界で活躍する写真家・井津建郎が創設し、当館が支援する「ラオ・フレンズ小児病院」(ラオス)と、東日本大震災の被災者支援団体「むすびば」(山梨)に寄付します。
■参加費: 一般 2,000円(入館料を含む) 小中学生は無料 友の会・会員は無料
■要予約: 定員 100名 / 全席自由
■お申し込み:8月1日(木)より受付開始 info@kmopa.com まで
★お申し込みはメールのみにて承ります。
★お申し込みは、お一人様2枚までとさせていただきます。
★申し込み先着順で、定員になり次第締め切らせていただきます。
★予約メールには、下記の必要事項をご記入くださいますようお願いいたします。
件名:チャリティ・ライブ予約
予約人数(2名まで):
代表者の御名前:
緊急時のご連絡先(携帯など):
当館からの返信先メール・アドレス(予約メールとアドレスが違う場合):
■ピーター・バラカン プロフィール
1951年ロンドン生まれ。ロンドン大学日本語学科を卒業後、1974年来日。音楽出版社の著作権業務に就く。1986年よりフリーのブロードキャスターとして活動し、現在「ウィークエンドサンシャイン」(NHK-FM)、「Barakan Beat」(InterFM)、「ライフスタイル・ミュージアム」(Tokyo FM)、「ジャパノロジー・プラス」(NHK BS1)をはじめ多くのテレビ、ラジオ番組に出演している。 2014年からは、自身が監修する都市型の音楽フェスティバル「Live Magic」も開催。主な著書に『ロックの英詩を読むー世界を変える歌』(集英社インターナショナル)、『魂(ソウル)のゆくえ』(アルテスパブリッシング)『ぼくが愛するロック名盤240』(講談社+α文庫)などがある。http://peterbarakan.net/
■次回展示
山本昌男「手中一滴」(仮題)
Yamamoto Masao: Microcosms Macrocosms
会期:2019年10月5日(土)~12月8日(日)